私たち親の世代が小学生の頃…「10の位から借りてくる…」という表現で繰り下がり引き算を教えてもらっていませんでしたか?
確かに『借りてくる』という表現ってなんだろう…。なんて分かりにくいんだろう…。
4歳11か月の息子に繰り下がり引き算を教える際、とても苦労しました。なかなか理解が進まず…親子で試行錯誤した結果、なんとかマスターできました。
繰り下がり引き算で躓いているお子さまの少しでもお力になれたら嬉しいです。
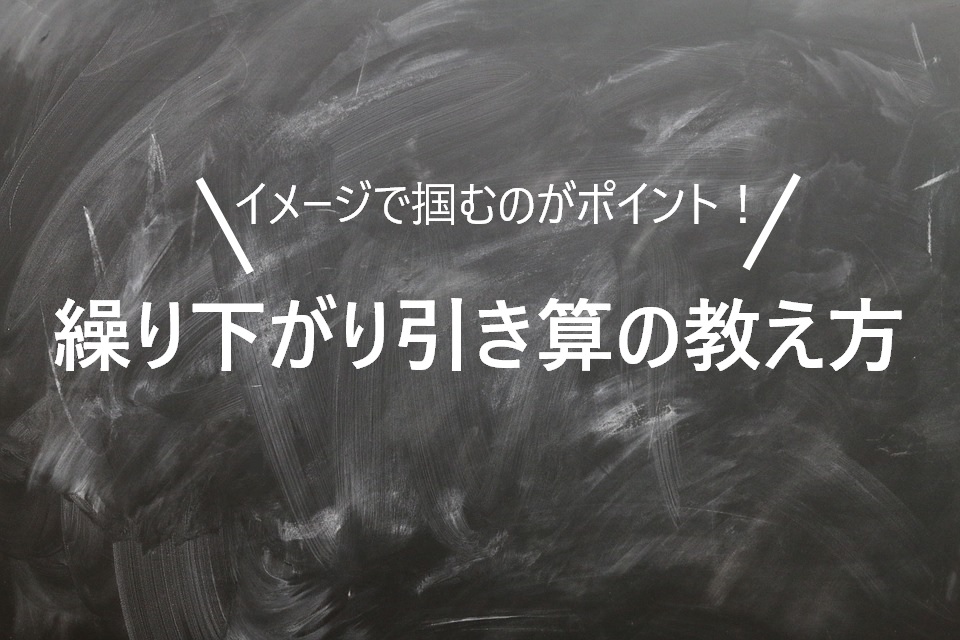
やはり大前提は「数の合成・分解」
繰り下がり引き算も、数の合成・分解をマスターしていれば、あとは考え方の問題なので、スムーズに頭に入っていけると思います。
数の合成・分解は大大大大大前提です!数の合成・分解は沢山のプリントも用意しています。スラスラ言えるようになった段階で、繰り下がり引き算に進むことをおススメします。

繰り下がり引き算の前に「両替」の考え方
以前の記事でお伝えしたように、我が家は「減加法」だけを教えています。「減加法」のやり方の詳細も出ているのでまずはこちらをご覧ください。

この中でやっているように、十の位から10を一の位に持ってきて、その10から引かせるということが重要なのです。10が十の位や一の位を行き来するということを両替の概念を使って慣らしていきましょう!!
実際のお金を使って、両替ごっこ?をやると、お子様もかなり食いついてくれると思います。
わぁー!3円のアメ買いたいのに、⑩円玉しか持ってないー!
すみません!お店屋さん!、⑩円玉を①円玉10個に両替してください!
と言って、10円と1円を両替してもらいます。
この時に、持っているお金は両替前と後では変わらないことをしっかり分かってもらうことが重要です!
繰り下がり引き算のやり方をイメージで掴む

一の位よりも、引かれる方の数(後ろの数)の方が大きいとき…そうだ!あの人の力を借りよう…!
スーパー10ぅ~!
あ!もしかしたら、冒頭の「借りる」問題…「10の力を『借りる』」という意味だとしたら…しっくりくるかも…!!

ここでは「引けないときは10から引く」ということをイメージで覚えてもらいます。
そういえば、あ!もしかしたら、冒頭の「借りる」問題…「10の力を『借りる』」という意味だとしたら…しっくりくるかも…!!
息子に繰り下がり引き算を教える時は、こんなのも活用していました。

PowerPoint資料のダウンロードや詳しい使い方等はこちらにまとめています。
何度かやって流れが分かってきたら、最後には息子に先生になってもらいます。「人に教える」というのも、習得への近道な気がします。
①と②でとにかく「10の力を借りる!」「10で引くと簡単だ!」ってことを印象付けます。
【がんプリ】繰り下がり引き算の基礎
わが子は繰り下がりの引き算習得するのに、すごく苦労しました…。
でも、とにかく楽しくイメージを付けてもらうことで、徐々に理解が進んだと記憶しています。
時間はかかりますが、ゆっくり着実に進めていくことで、苦手意識を持たずにマスターできるはずです。
物語風のプリントになっています。親子で楽しく進めて下さい!



引かれる数が10と何に分かれるかを理解する

引かれる数が10と何に分かれるかを何度もやってもらいます。
初めのうちは⑩円玉と①円玉を書いてあげて、⑩と何かに分けるということは⑩だけ1個なくなる(=①は変わらない)ということを理解してもらいます。
もし、「難しい」とか「分からない」というお子様がいたら(※息子は「難しい」と言っていました…)、魔法の言葉を言ってあげましょう!

大丈夫!これすっごく簡単な方法があるから!何か気が付かない?
鋭いお子様は気が付くことでしょう…(※息子は気が付きませんでした…)
「10」と何かに分解するということは、一の位は変わらずに、十の位だけ数がひとつ小さくなるのです。
気が付かなくても…
「あれ?⑩と何かに分けるってことは…十の位の数って、どうなってる…?1が0でしょ?これは3が2でしょ?…」
などど、誘導するようにして「自分で気が付かせる」ことが大事です。
そして、十の位を消してその一つ前の数字を右上に書くと分かりやすいことを教えてあげると、魔法のようにスラスラと出来ていきます。大人から見ると何てことない当たり前のことですが、子どもは自分で気づけたこと、難しかった問題があっという間に簡単にできるようになったことがすごくうれしく感じるはずです。
【がんプリ】10と何に分かれる?
理解しているお子様は飛ばしても大丈夫ですが、しっかり理解することで筆算にも繋がってくるので是非「遠回り」ではなく「近道」と思って取り組んで見て下さい!


繰り下がり引き算プリントをする時は、声かけをしてあげて


とここまでスムーズに出来るようになるまで、何度も何度も繰り返し練習しました。その際、慣れるまでは、繰り上がりたし算同様に、横から声掛けをしてあげていました。
例えば… 73ー8= を解く時…



一の位は引けると思う?引けないと思う?



「3」ー「8」で「8」の方が大きいから引けないと思う…



引けないときはどうするんだっけ?



10からひく…そのためには、十の位を6にして・・・



そうそう!10から引くと簡単なんだよね!10-8は?



8と仲良しは2だから2!



次はどうするんだっけ?



残っている63と2を足すから、一の位が5で…
答えは65!
こんな感じで細かく声掛けをしていました。
【がんプリ】繰り下がり引き算の練習








マスターしたら是非、こんなプリントにもチャレンジしてくださいね♬


