息子が5歳前に繰り下がり引き算を始めましたが、理解するのにとても苦戦しました。
なぜならば、私自身が繰り下がり引き算をきっちりと理解していなかったからです。
皆さんが無意識にしている「繰り下がり引き算」は「減加法」ですか?「減減法」ですか?
繰り下がり引き算を家庭で教えるためには、まずは教える側の大人がきっちり理解することから始めましょう!
繰り下がり引き算のやり方①減加法
繰り下がり引き算には大きく分けて2つの方法があります。まずは減加法。
①引かれる数を「10」と残りの数に分解する

②「10」と引く数で計算する(減)

③ ❷の答えと最初に分解して残った方を足す(加)

10-8=2(減)
3+2=5(加)
ということで「減加法」です。
この減加法のデメリットは、引き算なのに「足し算」が入っているという点です。混乱してしまう子もいるかもしれませんね。
繰り下がり引き算のやり方②減減法
①引く数を、「引かれる数の一の位の数」と残りの数に分解する

②引かれる数と分解した数字を計算して、引かれる数の一の位を0にする(減)

③ ❷の答えから分解して残った数を引く(減)

13-3=10(減)
10-5=5(減)
2回引くので「減減法」です。
ただ、例えばこれが
33-8になった場合…
30-5を最終的にせねばならず、繰り下がり足し算に慣れていない子はここでまた躓いてしまう可能性があります。
繰り下がり引き算はどちらで教えるのがいいのか?
いくつか参考にさせて頂きます。
指導では,どちらの方法が児童にとってわかりやすいか意見の分かれるところですが,一般には,減加法のほうが計算しやすく,定着を図りやすいといわれています。教科書では,減加法で指導されています。ただし,計算の方法として減減法が児童から出てきたときは,認めてやることが大切です。
この方法(減加法)はあらゆる問題に対して、一貫して同じ操作で指導ができる。いわゆる繰り下がりの操作とはこの減加法である。筆算は、この操作が必要である。しかし、10の補数の理解が十分でない子どもでは、用いることが難しい。減法であるのに、加法が含まれるので、加法と減法の混同を招くこともある。
(中略)
繰り下がりのある減法計算は、2年以降の筆算を考えた場合、減加法が適しているため、小学校1年生の教科書では、減加法の考え方が示されている。そして、ほとんどの子どもたちはこの方法で習得していくことになっている。
(減加法と減減法)両方載せてある教科書は、子どもたちの 数学的な思考力を大切にしようという考えが強いのです。片方しか載せてない教科書は、まず確実に計算ができるようにすることが大切だという考えが強いのです。実は、これは、教育界における算数の指導法についての相対立する2つの考え方を、そのまま反映しているのです。
前者では、数学的な思考力を育てるために、子どもたちにいろいろな解き方を考えさせたり話し合ったりすることに時間をかけます。その分、どうしても反復練習の時間が少なくなりがちですし、算数の苦手な子が付いていけないということにもなりがちです。
後者では、確実に計算ができようにするために、やり方はどんどん教えて反復練習に時間をかけます。
その分、思考力を育てる面では手薄になりがちですし、算数が得意な子には物足りないということにもなりがちです。
一言で言えば一長一短です。
ですから、本当はこの両者は相対立するものではなく、相補うものなのです。
どちらかに偏りすぎることなく、バランスを取ることが大事だと思います。
色々と意見がありましたが、やはり基本は「減加法」のようです。
確かに「数学的な思考力を育てたい」ですが、「減加法」以外のやり方が染みついてしまうと戻すのが大変なようです。
4歳の息子にはまずは「減加法」をきちんと理解してもらい、その後自分のやりやすいやり方を開拓していってもらえればと思ったので、現段階では「減減法」には触れず、「減加法」だけをきっちりとマスターしてもらうことにしました。
具体的な教え方は、こちらをご参考になさって下さい。
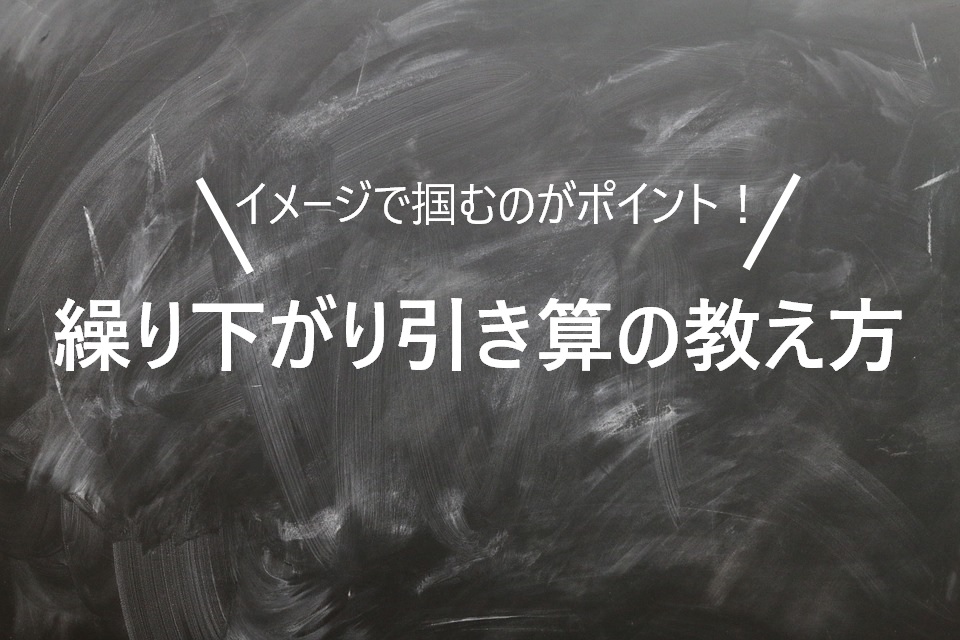
繰り下がりだけでなく、
分数や時計など、つまずきやすい単元の教え方もまとめています。
▶︎ 算数の教え方まとめはこちら
